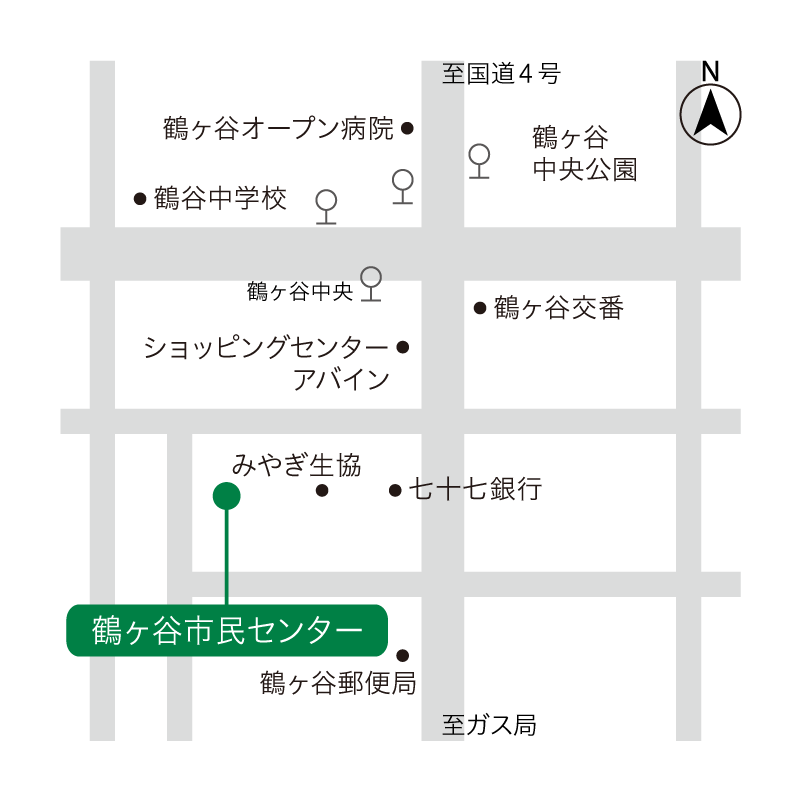ページID:4920
更新日:2025年3月25日

ここから本文です。
R6年度 鶴ケ谷ことぶき大学

令和6年度鶴ケ谷ことぶき大学
2025年2月28日


第9回 2月19日(水曜日)「昭和時代の仙台・鶴ケ谷の写真を見て語ろう」・閉講式 36名参加
令和6年度鶴ケ谷ことぶき大学の最後の講座は世話人会が担当です。
「1年間ことぶき大学生として在籍して、もっと受講生同士がお話ししたり、交流する機会がほしい」との声を受けて今回の企画に至りました。
お菓子とお茶をいただきつつ、風の時編集部代表 佐藤正実さんを講師にお招きして、昭和時代の仙台駅や鶴ケ谷の宅地造成の初めの頃の写真を見ながら、お互い自分の体験や思い出を語りあい、会場内は和やかな雰囲気で進行していきました。
続く閉講式では、鶴ケ谷市民センター館長から受講生を代表して世話人会代表へ修了証が授与されました。
受講生の皆様 今年1年鶴ケ谷ことぶき大学を積極的に受講していただきありがとうございました。
来年度もまた元気にお会いしましょう。
アンケート
- 世話人の皆様の毎回のご尽力に感服しました。とても内容の豊かな内容で毎回実施されたと思います。
- 鶴ケ谷団地も50年を経過して景観が一変しました。
- 懐かしい写真を見て昔のことを思い出しました。鶴ケ谷も賑わっていた時期もあり、時代の流れを感じます。
- 私の知らない鶴ケ谷の変わりようを見ることが出来ました。いろいろな思い出話しに花が咲き、いい街に変わったなーと写真を見てあーだ、こーだと言える方がとても羨ましいです。
- 世話人の皆さん、本当にご苦労様でした。ありがとうございました。

第8回 1月15日(水曜日)新春コンサート~ピアノとサックスによる~ 33名参加
令和7年の講座は「ピアノとサックスによる新春コンサート」で始まりました。演奏していただいたのは「Music life」として活躍している大道美由貴さんと千葉千寿子さんのお2人です。
大道さんのサックス演奏は、どこで息継ぎをしているのか分からないほど一息が長く、深い余韻が続き、千葉さんの演奏は、ピアノがまるで生き生きと歌っているような演奏で、会場の皆さんも、リズムに合わせて思わず口ずさんだり、手拍子をしたりと演奏を楽しんでいるようでした。
60分の演奏があっという間に感じられ、皆さんからは”大好評”の声がたくさん寄せられました。
アンケ—トより
- 短い時間であったにもかかわらず頭の中では何十年という長い月日がめぐり、すごく懐かしく幸せなひと時でした。
- 選曲が素晴らしくトークも上手で引き込まれました。目頭があつくなりウルウルして、一年がよい年になる予感がしました。
- ソプラノサックス、初めて聞きました。青春を思い出し若返りました。
- サックスというとジャズと結びついてしまうが、いろいろ聴かせていただいて楽しかった。
- 新春にふさわしいピアノ、サックスの演奏とてもすばらしかった。感激です。また聴きたい。


第7回 12月18日(水曜日)講話「大相撲を10倍楽しむ方法」33名参加
今回の講師は東北放送株式会社 ラジオ局アナウンス部 守谷 周さんでした。
日頃、テレビの番組やスポーツ放送などでお姿を目にすることが多い守谷さん。
受講生の中には直接お話を伺える今回の講座を楽しみにされていた方も多くいらっしゃいました。
守谷さんは小さな頃から大相撲に興味をもって、相撲に関する本を読んだり、DVDコレクションの鑑賞で知識を深めてきたそうです。
初代横綱とされる明石志賀乃助から現横綱の73代照ノ富士春雄まで、一人ひとりのエピソードを交えながら分かりやすく紹介して頂きました。
「横綱」という称号はそもそも「大関」の中でも最高の称号のことで、1789年、谷風、小野川が吉田司家から横綱土俵入り免許を得たことから「横綱」が始まったのだとか。
また、今では相撲は国技と言われますが、「国技館」でやっているから「国技」といわれるようになっとか。
土俵の「とくだわら」もともと土俵にたまった水を土俵の外へ掃き出すためにあるけれど、力士は上手く使って回り込んで勝つために使うとか。
このほかにも知らなかったことがいっぱい紹介されたので、これからの相撲の見方が楽しみになったと感想がありました。
アンケートより
- 相撲が好きで夕方の番組を見るのを楽しみにしています。これからは勝負だけでなく別の視点にも注意しながら見ようと思います。
- 相撲はあまり興味がなかったのですが、お話が上手で分かりやすかったので興味が持てるようになりました。さすがアナウンサーですね!歯切れがよく聞きやすかったです。
- ラジオ・テレビの司会などおなじみの守谷さん。ファンの私は、最後まで興味深く楽しめました。
- 相撲の歴史を初めて知りました。楽しい講座でした。


第6回 11月20日(水曜日)講話「生涯現役!楽しくストレッチ」 32名参加
スポーツプログラマー藤森 弘一さんから、普段の身近な場所でできるフレイル予防のストレッチを教えて頂きました。
「フレイル-サルコペニア-ロコモティブシンドローム-生活習慣病—成人病」
これは身体を動かさないと陥りやすい身体の一連の状態を指すのだそうです。
「横断歩道を渡る時は、45センチの線を意識して歩幅を広く」、「自宅の洗面台や台所の流し台、食堂テーブルの高さが筋肉を動かすのにちょうどいい」など、ちょっと気を付けながら、こまめに身体を動かすポイントが紹介されました。
「歩くときは肘を後ろにひくことを意識して」「椅子からゆっくり立ち上がる動きはスクワット」「インナーマッスルを意識して動かして」など、何気ない動きの中にもたくさんの注意点があることを教えて頂きました。
講座の終わりには「市民センターの玄関を出るまでは、背中を意識して歩きましょう!見返り美人ですよ」とお話しがあり、出席した皆さんは笑顔でうなづきながら会場を後にされました。
アンケートより
- 自分にできる時間に行える動きを実行したいと思います。
- 家事をする時、テレビを見ながらでもできることがあり、これから実行しようと思いました。
- 楽しく参加できたのでラッキーでした。
- 正しい姿勢の大切さが分かった。歩くことは人間生活の基本、なるべく歩くことを心がけようと思う。
- 継続して行動できるようにすることが重要だと思います。
- 今日学んだ運動を続けて足・腰の痛みをなくそうと思います。


第5回 10月16日(水曜日)館外学習「七十七銀行金融資料館」見学 30名参加
約20年ぶりに3種類(一万円、五千円、千円)の紙幣のデザインが新しくなり、一万円札は渋沢栄一に交代になりました。
今年の館外学習は、渋沢栄一が七十七銀行の前身、第七十七国立銀行設立に深くかかわった資料が展示されている、「七十七銀行金融史料館」を見学しました。
銀行の金庫室の大扉を再現したという入口の大扉から入り、資料館の中は、普段目にする機会が少ない貴重な資料が豊富で、お金や銀行の成立ち、体験コーナーなどがあり、皆さんは珍しい展示資料をじっくり見学できたようです。
アンケート
- 七十七銀行の歴史とお金の歴史、仙台市の時代の変化が分かりとても興味深かったです。
- 銀行の成立のあゆみがわかり振り返ることが出来てよかった。
- とても参考になった。特に、今の若者や、子どもたちににはぜひ見せたい、知らせたい展示内容だった。
- 日本の紙幣や世界の紙幣が展示されていて楽しかった。
- 歴史などきちんと整理して展示してあり分かり易かった。
- 七十七銀行と渋沢栄一の偉大さを改めて実感しました。非常に勉強になりました。


第4回 9月18日(水曜日)「チョコレートの世界へようこそ」34名出席
(株)明治 北日本支社 食育担当栄養士 阿部 裕子 様をお迎えし、カカオ豆の生産からチョコレートとして食べられるまでの一連のお話をお聞きしました。世界のカカオの年間消費量第1位スイス、2位ドイツ…日本は18位。年間生産量は日本は第3位とのこと。
カカオ豆の中のポリフェノール含有量や、シニア世代の健康志向の高まりにより日本のチョコレート消費量は毎年伸びていて、そのため生産量も伸びてきているのだそう。
(株)明治の現地でのカカオ豆の生産農家への技術支援や現地での社会貢献の取り組みなども紹介されました。
普段何気なく口にしているチョコレートですが、これまで気づかなかったチョコレートへの理解を深める機会になりました。
アンケートより
- 大好きなチョコレート。興味深く、楽しい時間でした。
- カカオ豆からチョコレートができるまで、初めて知ることが出来ました。
- おやつとしてのカカオの認識しか特になかったので奥の深さに感動しました。
- 美味しいチョコレートを食べると幸福な気持ちになり、いつまでも食べられるような世界であって欲しいと痛感しました。
- ガーナ共和国のカカオ農家への技術支援、生活、教育支援に力を入れていることを初めて知りました。色々な分野に社会貢献されていることに感動しました。
- 試食させていただいて良かった。これからは産地などにも気をつけて購入しようと思いました。


第3回 7月17日(水曜日)「土人形って何だろう」34名出席
仙台市博物館学芸普及室・相原裕起子先生から仙台藩における焼物の始まりと堤人形の歴史を説明していただき、続いて皆さんで土人形の絵付けを体験しました。
一人ひとり筆で絵の具を塗って思い通りの人形に仕上げます。
「うーん、むずかしい」「にじんでしまった」など溜息ともとれる悪戦苦闘の様子でしたが、中には着物の柄や顔の表情を小筆を使って細やかな線で仕上げる方もいらっしゃいました。
今回の内容を楽しみにしていたという方もいたり、完成した作品をじっくり眺めたり、出席した全員が時間内にオリジナル作品を完成させました。
アンケートより
- 思い通り上手に絵の具を塗れませんでしたが、楽しくやれました。リニューアルした博物館へまた行ってみようと思います。
- 面白かったです。異次元の世界にまた参加したいと思います。
- 初めてでしたがいろんな工夫を考える時間もありとても楽しくできました。
- 人形の絵付けは本当に難しかったです。でも自分の表現ということで勉強になりました。
- 物づくりはとても楽しかったです。また、いろいろ体験したい。

第2回 6月19日(水曜日)「転倒予防・ロコモティブシンドロームとその対策」37名出席
仙台オープン病院 リハビリテーション室 副技師長渡辺亮様から講話と家庭でも手軽にできるトレーニング方法を紹介していただきました。
受講生の皆さんはロコモチェック(簡易チェック)やスクワットなどその場で体験し、今の自分の体の状態を把握することに積極的でした。
中には先生の説明を大きくうなづきながら聞いている方、椅子に腰かけたまま先生のお話しのとおり足を動かそうとする方など、皆さんの関心の高さがうかがえました。
アンケートより
- 1週間ほど前に歩いていて段差で転び痛い目に合いました。今日のお話しはとてもためになり自分でもやってみようと思います。
- 自分の体力の劣化にびっくりしました。転倒予防をしっかり自覚しました。
- 日々少しづつ努力をして筋肉の貯金をしていきたいと思った。
- 大変参考になりました。年とともに衰えはじめているので、その前に話を聞いていればと思いました。今からでも遅くないか、出来ることから始めます。
- 食事・運動・社会活動をバランスよく習慣づけて転倒・寝たきりだけは絶対に避けたいと思う。
- リハビリ施設を利用しているので大変分かりやすく理解できた。
- 簡単なロコモ体操を教えてくださってとても良かったです。杖の付き方についてもよく分かりました。

第1回5月15日(水曜日)「安養寺という寺」41名出席
今年度の鶴ケ谷ことぶき大学がスタートしました。今野館長から「人生100年時代。人と人、人と地域が助け合いながら絆のある地域づくりを目指し、明るく楽しいものにしていきましょう」とあいさつがありました。
引き続き、鶴ケ谷地域で活動している団体「まるっとつるがや」の小野さんと篠原さんから、「安養寺という寺」というテーマで、平安時代から江戸時代の資料にみられる「安養寺」の説明をいただきました。
現在の「安養寺」は地名として残っていますが、古い資料をもとに、詳しい説明を聴く機会がなかなか少ないため、出席した皆さんから興深かったなどの感想をいただきました。
そしてオリエンテーションでは年間学習計画の説明、世話人選出と、今後に向けた皆さんの意気込みが伝わっていました。
アンケートより
- 有意義な歴史の講座で参考になりました。
- この近辺の地名が多く出てきたので大変興味をもちました。
- 安養寺の由来が少しわかったように思います。
- 大変面白かったので、続きを楽しみにしています。
- 仙台在住23年、知らないことが多く、安養寺も良く知らなかったので興味深かったです。
- 第1回目なので無事世話人も決まりこれから楽しみに参加したいと思います。