ページID:11984
更新日:2025年12月4日

ここから本文です。
令和7年度 みんなで守ろうホタルの里

豊かな田園風景が広がる坪沼地区は蛍の里として知られていますが、最近は自然環境や生活様式の変化、光害等の影響で蛍が少なくなっています。そこで20年程前から地元の有志が立ち上げた「ふる里坪沼実行委員会」が中心となって、蛍が自生できるよう水辺の環境を整えたり、蛍のえさになるカワニナを増やしたりすることで、本来坪沼に生息している蛍を呼び戻す活動を続けています。
11月16日(日曜日)蛍生息地でのいきもの調査と水路整備
“ゲンジボタルの自生地を整備する”ことを目標に据えた活動に切り替えてから、前回の6月に続き、2回目のいきもの調査を行いました。
むかい*いきもの研究所の向井康夫先生のご指導の下で、3月に放したカワニナの成貝108匹が、夏を越して生存しているのか、繁殖しているのかを、今回の調査で確認することになります。

調査は、水路の上流・中流・下流と、いくつかのポイントを設け、水底の泥ごと掬って、その中にどんな水生生物がどれ位いるのかを調べるという方法です。泥ごと掬うので、水の中にいる生物も底に潜んでいる生物も見つけることができるというわけです。
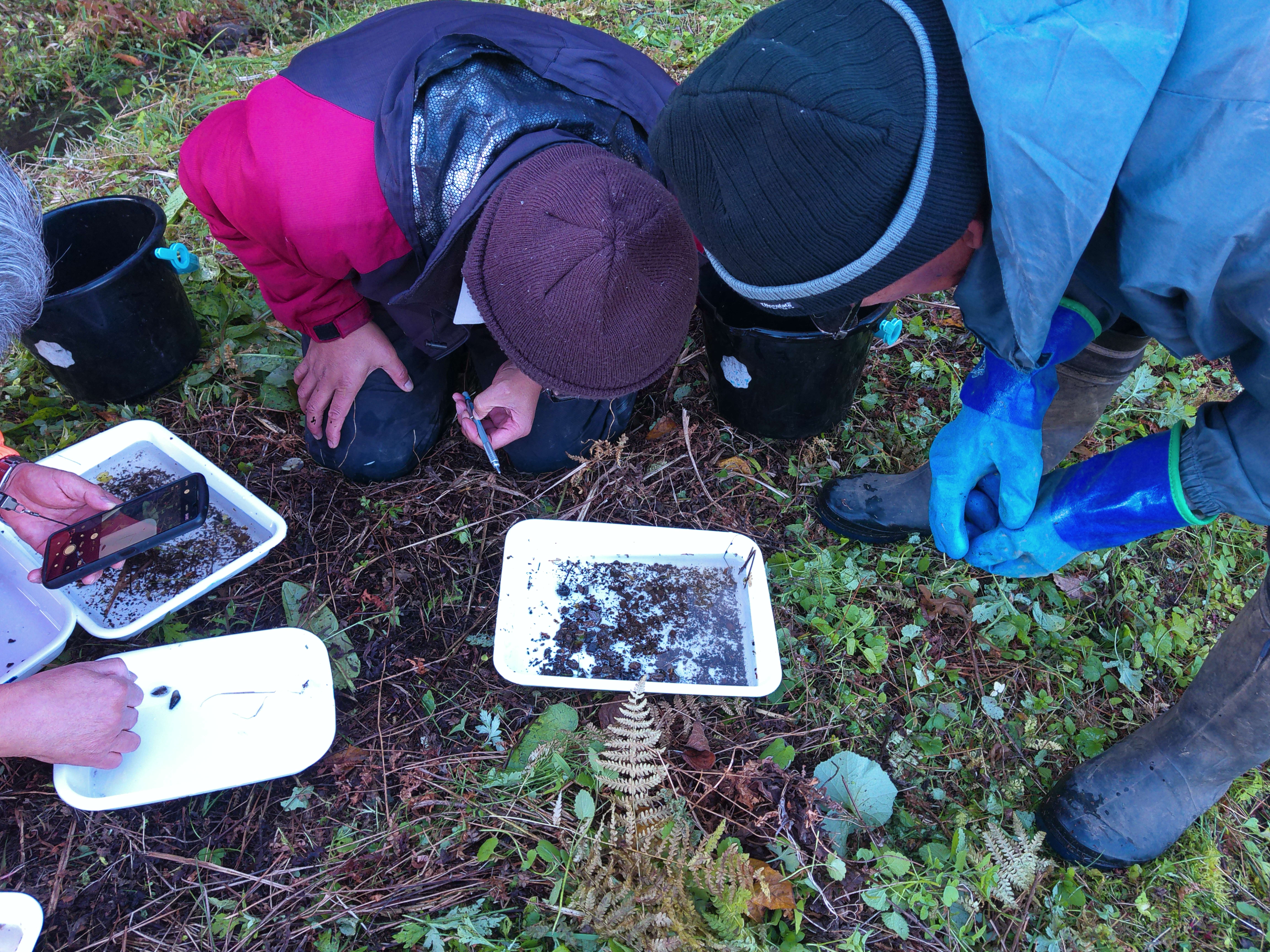
トレーに移して調べた結果、カゲロウやトンボの幼虫など、6月の調査時よりはるかに多い種類の生物と、カナニナの子貝を多数確認することができました。一同安堵。さらに調査を進めたところ…

蛍の1齢、2齢、3齢幼虫がそれぞれ見つかりました!これは、参加者全員なにより嬉しい発見でした。

先生のアドバイスにより、データロガーという器具を水中に沈めて、水温を自動的に記録することも始めました。これにより、水量が少なくなっていないかや、水量の変動をおおまかに把握できるようになるそうです。
調査結果を出し合ったところ、流水環境は良好な状態に保たれており、カワニナにとってすみやすい環境になりつつあることがわかりました。
今後、ホタルの里として整備を進めていくには、今回行ったカワニナ放流実験のように、数々、試行錯誤を繰り返していくことになるかと思われます。それでもこの日の活動で、ゲンジボタル定着の可能性が見えてきたことを、皆で確認しあうことができました。
6月28日(土曜日)蛍観察会

坪沼八幡神社において「蛍と平家琵琶の夕べ」を開催しました。源氏と平家にまつわる伝説がある坪沼で、ゲンジボタルの鑑賞会と平家琵琶の演奏会を併せて行っているおまつりです。今回で35回目となるこの時期恒例の行事で市内外からたくさんの参加者で境内が賑わいます。
蛍観察の前に、定義ホタルの里づくり実行委員会の梅津先生から、蛍の種類や生態について詳しく教えていただきました。蛍が生息できる場所は水環境ばかりではなく、多くの条件が必要で、坪沼はその環境が揃っている地域だとのこと。みんなでこの自然を大切にしていきたいものです。

蛍が見ごろになる時間は8時すぎ。それまでは神社の境内で蛍を見ていただくことができるよう観察ケースを設置し、実行委員が蛍について説明をしています。まつりの終わりには大勢の見学者が見守る中、ケースを開け放ち、その瞬間、ワーッという歓声とともに、蛍が夜空に飛び立ちました。

日没後、あたりが暗闇に包まれた頃が蛍観察会の始まりです。実行委員の先導で境内から10分程散策しながら、自然の中を飛ぶ蛍を見学しました。曲線を描いて儚げに光る蛍はとても幻想的で、子どもも大人も目を輝かせて見入っていました。
この蛍観察会には約200人の方が参加し、それぞれの記憶に残った夜になったのではないでしょうか。ここに至るまでは、長年にわたり、蛍生息地の水辺の管理や観察路の整備に尽力されてきた地域の力があってこそかと思われます。この美しい風景がいつまでも見られることを願ってやみません。
6月24日(火曜日)竹あかりワークショップ

6月28日に坪沼で開催される「蛍と平家琵琶の夕べ」では、会場となる坪沼八幡神社の境内に竹あかりをかざり、来場される方をお迎えしています。その竹あかりは坪沼で開校3年目になるろりぽっぷ小学校の児童と町内の方々が協力して手作りをしています。この日は地域の竹林で材料となる竹を切り出しました。
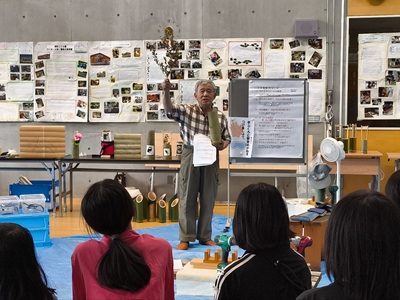
6月24日(火曜日)ろりぽっぷ小学校で竹あかりワークショッを開催しました。竹細工名人の徳田さんほか、町内会長さんらが先生です。

今年の竹あかりは子どもたちが描いた絵をもとに図案化したもの。自分の絵が作品になるとあって子どもたちはより丁寧にドリルで穴あけをして作品を仕上げました。
完成後「難しかったけれど、楽しかった!」と話す、たくさんの笑顔が見られました。

一人ひとりの思いが込められた竹あかりは「蛍と平家琵琶の夕べ」の会場に飾られました。心がこもった優しいあかりでした。
6月7日(土曜日)蛍生息地の整備

本日は蛍生息地の整備活動の日。ふる里坪沼実行員会の面々に加え、ご近所の方も集まってくれました。この蛍生息地は田んぼだったところに水路を作って整備していた場所で、一昨年までは、流水の水生生物やカワニナも多数生息していたのですが、昨夏の酷暑で水路が水枯れしてしまうという事態が発生してしまいました。それがきっかけとなり、水生生物の専門家・むかい*いきもの研究所の向井康夫先生にアドバイスをいただくことになりました。
先生のご指導の下、水路の流れを整え、水路の入り口近くに108匹のカワニナを新たに放して3か月後のこの日、そのカワニナが生息しているか、小貝が生まれているのかの調査を行いました。
見つかったカワニナはおよそ30匹。見つけた場所もほうぼうに散らばっており、水底にもぐっているカワニナもいることを考えれば、想定以上に見つかったと言えるとのこと。この結果、流水の環境が整いつつあることがわかり、一同胸をなでおろしました。

作業の後の話し合いで先生から様々なアドバイスをいただき、これまで試行錯誤してきた活動の、今後の方向性が見えてきたように思われました。環境等の変化により少なくなった蛍を呼び戻す活動に近道はなく、段階を踏んで蛍が生息できる環境を整えていくことが大切だという認識を全員が共有できたのではないかと思います。
講座情報
| 内容 | 坪沼の蛍生息地での環境整備に加えて以下の活動を行っています。 ・蛍観察路の整備 ・蛍生息地の水生生物調査 ・蛍生息地の生き物観察会 ・蛍観察路を照らす竹あかりづくり ・蛍観察会 |
|---|---|
| 開催日 | 通年で実施 |
| 対象 | おとな |
