ページID:4762
更新日:2025年3月25日

ここから本文です。
令和5年度「もっと知ってもっと好きになるわたしのまち」第4回目を開催しました
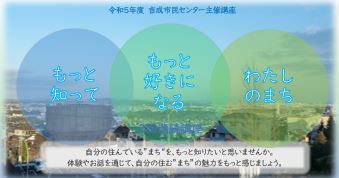
もっと知ってもっと好きになるわたしのまち第4回目を開催いたしました
2024年2月12日

2月12日 第4回目「仁田谷地・大石ヶ原を読み解く『縄文地名ノオト』~大地を言祝ぐ『ことば』~」を開催いたしました。
東北文化学園大学 工学部 建築環境学科 教授 八十川淳先生をお招きしました。
先生は縄文時代に使われていた言葉の音と地形などを手掛かりに地名を解読する研究をされており、吉成地域に古くから残る地名の本来の意味についてもその説に基づいて読み解いていただきました。
例えば、「仁田谷地」は「nitat iworchiw」という音で、「nitat(湿地あるいは林間湿地) iwor(神々の住む世界)chiw(水流)」つまり「狩や漁の場あるいは燃料建材衣類など生活用材の調達の場」となります。
他の地名についても、かつての人々が自然や生きものに対して強い畏敬の念を抱いていたことを前提に読み解かれていて、本来の意味は人々の生活に根差したものであるということが共通していました。
【アンケートより】
- 八十川先生の講座は座学やまち歩きなど何度か参加させていただいていますが、毎回目からウロコな内容で、新しい発見があります。今回も日頃からなじみのある地名に深い意味があることを知り、早速復習したくなりました。
- 新しい感覚を持ちました。地名をおもしろい解釈で分析されていて、良い勉強になりました。
- 大変興味深い分野で、地名を通じて日本古代史(地域史)を読み解く可能性に夢があります。


9月30日 第3回目「わたしのまちの先生に手織りを教わります!」を開催いたしました。
講師は、「染織工房 琉」の中村鉄弥先生です。
前半は、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)から作られる工程は全世界共通で、完成まで3つの構成で成り立つ、という織物についてお話を聞きました。また、糸や養蚕についての貴重なお話も聞くことができました。
後半は、先生のご指導のもと、ひとりずつ小さなフレームでミニミニ手織り体験をしました。
何種類かの毛糸から、それぞれが気に入った緯糸を選んで織り、世界に一つだけの自分だけの織物を作ることが出来ました。
【アンケートより】
- 「命をいただいている」ということ(特に”かいこ”のこと)は頭になかったので、印象に残りました。
- 服でも住宅でも、自然にもどる(かえる)のは大切だと思いました。
- 手織りは初めてで難しいと思っていましたが、楽しく出来て良かったです。
第2回目 「わたしのまちのいつものお店の店長さんのおはなし」

8月26日(土曜日)みやぎ生活協同組合 国見ケ丘店の森忠信店長を講師にお迎えし「わたしのまちのいつものお店の店長さんのおはなし」を開催いたしました。
みやぎ生協国見ケ丘店は1994年10月6日(木曜日)にオープンし、今年で29年目だそうです。オープン時と現在の写真を見比べて、当時を思い出す受講生もいました。
商品が売り場に並ぶまでの各部門の手順や厳しい衛生管理、みやぎ生協全体の取組などは、店長が撮って下さったたくさんの写真から詳しく知ることが出来ました。
また、森店長が異動してきて感じたこの地域の特徴や震災時の経験談に、受講生は大変興味を持ち、真剣に耳を傾けていました。
【アンケートより】
- 食の安全のための工夫や様々なルールに従って作業していることが分かりました。
- 大震災時の話は、当時の自分の経験と重なって興味深かった。
- 衛生管理がしっかりされていることが印象に残りました。
第1回目 「わたしのまちの活牛寺で座禅体験」

7月29日(土曜日)吉成山活牛寺本堂において、「わたしのまちの活牛寺で座禅体験」を開催いたしました。
活牛寺の菅原一芳住職から、足の組み方、坐蒲の使い方、姿勢や呼吸など、座禅について丁寧に教えていただきました。
「入ってくる音にはただただ耳を傾ける。ただただ感じる。」「頭の中でいろいろ思うものは、浮いては消え浮いては消えるあぶくのようにして、考えずただただ集中する。」「計らい事はやめて、ただ命として座っているだけ。」などの心構えも教えていただき、まず10分間の座禅をしました。その後休憩をはさんで20分間の座禅をしました。座禅の後には、住職の永平寺での修行時代のお話や活牛寺の歩みなども聞くことができました。
大変暑い日でしたが、セミの声や時折吹き抜ける風を感じ、流れる汗をも忘れる貴重な時間を過ごすことができました。
【アンケートから】
- 初めての体験でした。セミの声、すずしい風、自然との一体感を得ました。
- 無の心の大変さ、難しさを感じました。とても良かったです。
- 住職の永平寺での修行のお話が興味深かったです。
