ページID:11562
更新日:2025年12月6日

ここから本文です。
令和7年度 北山さんぽみち⁻過去から未来へ
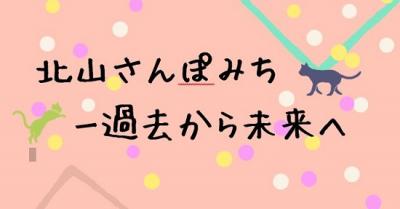
北山を流れた「北の小川跡~北山の流れ跡」
12月4日(木曜日)10時00分~12時00分
北山三川(北の小川・中の小川・南の小川)のうち、今回は北の小川跡を辿りました。昭和39年の地図を頼 りに、ここが私たちが歩ける一番の上流と思われるところを探し出し、下流に向かって散策しました。民家の前に不自然なコンクリやアスファルトを見つけては、「暗渠の蓋だね」などと話し合い、その根拠の配管やU字溝を見つけては自分たちの推理が正しかったことに喜び合いました。小川跡の途中にある大法寺にお邪魔して、本堂内部を見学させていただきました。台座を含めると2メートルを超す、坐像では市内最大の木造阿弥陀如来坐像や、楽器を奏で舞う飛天が一面に描かれた天井な
りに、ここが私たちが歩ける一番の上流と思われるところを探し出し、下流に向かって散策しました。民家の前に不自然なコンクリやアスファルトを見つけては、「暗渠の蓋だね」などと話し合い、その根拠の配管やU字溝を見つけては自分たちの推理が正しかったことに喜び合いました。小川跡の途中にある大法寺にお邪魔して、本堂内部を見学させていただきました。台座を含めると2メートルを超す、坐像では市内最大の木造阿弥陀如来坐像や、楽器を奏で舞う飛天が一面に描かれた天井な ど、荘厳さと美しさに言葉が出ませんでした。境内には、企画会議で学習した叢塚(くさむらづか)や、鬼瓦名工「伊藤喜三郎氏」より寄進された七福神などがありました。そこから川跡に戻り、中の小川との合流点の恩慶寺を経て、北山の流れと呼ばれている川跡の昭和39年版地図での始まりの地に着きました。住宅地の真ん中に川跡以外に入口がないぽっかりとした空き地。周りをぐるっと水の流れの跡が感じられ、塀越しに隣の家の方とお話ができました。流路のところを「そういえば昔は水が流れ
ど、荘厳さと美しさに言葉が出ませんでした。境内には、企画会議で学習した叢塚(くさむらづか)や、鬼瓦名工「伊藤喜三郎氏」より寄進された七福神などがありました。そこから川跡に戻り、中の小川との合流点の恩慶寺を経て、北山の流れと呼ばれている川跡の昭和39年版地図での始まりの地に着きました。住宅地の真ん中に川跡以外に入口がないぽっかりとした空き地。周りをぐるっと水の流れの跡が感じられ、塀越しに隣の家の方とお話ができました。流路のところを「そういえば昔は水が流れ てたね」と思い出してくださり、川跡だった確信がここでも高まりました。幅広く舗装された道になっていたり、一列にしか通れない細い道になっていたりする暗渠を辿り、北仙台にある仙台浅草へ、またそこから四ツ谷用水支流「九番町堀」が梅田川に注ぐ杉戸橋まで歩きました。梅田川と四ツ谷用水支流と仙台鉄道跡と道路が交差する不思議な地形を見学して、長い距離の本日の散策を終えました。
てたね」と思い出してくださり、川跡だった確信がここでも高まりました。幅広く舗装された道になっていたり、一列にしか通れない細い道になっていたりする暗渠を辿り、北仙台にある仙台浅草へ、またそこから四ツ谷用水支流「九番町堀」が梅田川に注ぐ杉戸橋まで歩きました。梅田川と四ツ谷用水支流と仙台鉄道跡と道路が交差する不思議な地形を見学して、長い距離の本日の散策を終えました。
北山を流れた「中の小川跡」下流編
11月6日(木曜日)10時00分~12時00分
 中の小川上流散策から一週間が経ち、今度は下流を散策しました。市民センターを出てほんの少し北に向かった道路が、小川を渡る橋だったことが昭和39年の地図から読み取れました。その小川の跡を辿ってくねくねした裏道を歩いていくと、和敬保育園と昌繁寺の間に出ます。そのあたりは川幅がかなりあったように地図に記載されていました。ここで川跡の途中ですが、新坂町の昌繁寺に立ち寄りました。仙台藩の頃の有名な家臣や茶道家、乱舞衆、西洋砲術家、北山附木で有名だった方のお墓などを探し、また
中の小川上流散策から一週間が経ち、今度は下流を散策しました。市民センターを出てほんの少し北に向かった道路が、小川を渡る橋だったことが昭和39年の地図から読み取れました。その小川の跡を辿ってくねくねした裏道を歩いていくと、和敬保育園と昌繁寺の間に出ます。そのあたりは川幅がかなりあったように地図に記載されていました。ここで川跡の途中ですが、新坂町の昌繁寺に立ち寄りました。仙台藩の頃の有名な家臣や茶道家、乱舞衆、西洋砲術家、北山附木で有名だった方のお墓などを探し、また 仙台三十三観音五番札所の観音堂も見学しました。さて、川跡に戻り散策を続けます。地図では保育園から道路を渡り住宅地を斜めに通っているように見え、今は川跡はないかと思われましたが探してみると住宅地の間を縫うように空き地があり、あきらかに川跡だったことがわかりました。地図上で川跡は道路に出て、南に折れ曲がったところで唐突に終わってしまいました。実際の道路でも不自然に道路の幅が変わっていて、小川が間違いなくここを流れていたのがわかります。中の小川探索
仙台三十三観音五番札所の観音堂も見学しました。さて、川跡に戻り散策を続けます。地図では保育園から道路を渡り住宅地を斜めに通っているように見え、今は川跡はないかと思われましたが探してみると住宅地の間を縫うように空き地があり、あきらかに川跡だったことがわかりました。地図上で川跡は道路に出て、南に折れ曲がったところで唐突に終わってしまいました。実際の道路でも不自然に道路の幅が変わっていて、小川が間違いなくここを流れていたのがわかります。中の小川探索 はここまでですが、近くの恩慶寺を見学させていただきました。恩慶寺の山門に載っている鬼瓦の隣に下に波模様のある球体の瓦があり、何を表わしているのか次回までに調べてみることになりました。敷地の奥に行くとからたちの木に実がなっていて、豊かな香りが漂っています。そこのフェンスの外側が堀になっていて、地図で確認すると12月に散策する予定の北の小川の一部のようです。中の小川と北の小川はこんなに近いところを流れていたことがわかり、12月の散策にも期待が高まりました。
はここまでですが、近くの恩慶寺を見学させていただきました。恩慶寺の山門に載っている鬼瓦の隣に下に波模様のある球体の瓦があり、何を表わしているのか次回までに調べてみることになりました。敷地の奥に行くとからたちの木に実がなっていて、豊かな香りが漂っています。そこのフェンスの外側が堀になっていて、地図で確認すると12月に散策する予定の北の小川の一部のようです。中の小川と北の小川はこんなに近いところを流れていたことがわかり、12月の散策にも期待が高まりました。
北山を流れた「中の小川跡」上流編
10月30日(木曜日)10時00分~11時30分
いよいよ北山を流れた小川跡を辿る散策に突入しました。市民センターの隣の東北大学国際交流会館の中に「中の小川」が流れて いた痕跡があります。昭和39年の地図と現地を見比べながら、草の中から一部露出しているU字溝を発見し、流れていたと思われる「その先」を探しました。震災後に建てた建物のぐるっと回ったフェンス沿いがちょうど小川の跡でした。しっかり残っている川跡に企画員も感心していました。途中「科学計測研究所発祥の地」の石碑を発見。これは、昔からあった碑が震災で壊れてしまい、新しく建立したもののようでした。さらに、地図からわかる川跡を辿ると、東北福祉
いた痕跡があります。昭和39年の地図と現地を見比べながら、草の中から一部露出しているU字溝を発見し、流れていたと思われる「その先」を探しました。震災後に建てた建物のぐるっと回ったフェンス沿いがちょうど小川の跡でした。しっかり残っている川跡に企画員も感心していました。途中「科学計測研究所発祥の地」の石碑を発見。これは、昔からあった碑が震災で壊れてしまい、新しく建立したもののようでした。さらに、地図からわかる川跡を辿ると、東北福祉
 大学の敷地の北脇を頂上まで登るようになっています。ここは昔「伊勢堂山」と言われていたところで、八幡小学校の校歌の歌詞にも出てきます。今でこそ住宅が立ち並んでいますが、昔は山だったことがわかります。標高が100メートル超で北山五山の70メートル超と比べてもかなり高いことがわかり、遠くは七ツ森まで見ることができました。そのあたりが中の小川の始まりだったと思われて、小川跡探索は終了しましたが、せっかく頂上まで来たのでそこから東に尾根沿いに散策を続けまし
大学の敷地の北脇を頂上まで登るようになっています。ここは昔「伊勢堂山」と言われていたところで、八幡小学校の校歌の歌詞にも出てきます。今でこそ住宅が立ち並んでいますが、昔は山だったことがわかります。標高が100メートル超で北山五山の70メートル超と比べてもかなり高いことがわかり、遠くは七ツ森まで見ることができました。そのあたりが中の小川の始まりだったと思われて、小川跡探索は終了しましたが、せっかく頂上まで来たのでそこから東に尾根沿いに散策を続けまし

た。途中、伊勢神明社を見学し、御嶽三吉神社へと進みました。この神社も見晴らしがとてもよく、中山にある仙台大観音をちょうど正面に見ることができます。またここには、戦時中に掘った「東北帝国大学科学計測研究所」の保管壕(防空壕)があります。令和6年度に調べていた「太陽炉と科学計測研究所」の最終確認をするためにも、懐中電灯を持って中に入ってみることにしました。壕の壁には、燭台を置くための窪みがあり、少し黒く煤けているのも確認できました。実際に書類を保管することはなかったそうですが、戦時中を偲ぶことができる貴重な遺跡を訪問でき充実した内容でした。今回も企画員は川跡を探すときに、「タモリさんみたいだね」とか保管壕では「去年調べた話だね」とか「一度来たところを歩くのがまた楽しい、知っているからこそだね」など感想を述べあっていました。11月6日は「中の小川跡」下流編、とても楽しみです。
市民企画会議
10月2日(木曜日)10時00分~11時40分
 4月の市民企画会議で決めていた、北山交流まつりに参加するための展示物を作成しました。4月10日に歩いた、「新坂通探訪 坂と桜とお寺さん」の時に調べた「新坂と新坂通」を中心に、年代ごとの地図で道路が変わった様子やきれいに咲いていた桜の花のマップなどを準備しました。
4月の市民企画会議で決めていた、北山交流まつりに参加するための展示物を作成しました。4月10日に歩いた、「新坂通探訪 坂と桜とお寺さん」の時に調べた「新坂と新坂通」を中心に、年代ごとの地図で道路が変わった様子やきれいに咲いていた桜の花のマップなどを準備しました。
 この写真は、年代の違う地図の同じ場所を探していて、「あっ、ここだ」と声が聞こえてくるようなベストショットです。
この写真は、年代の違う地図の同じ場所を探していて、「あっ、ここだ」と声が聞こえてくるようなベストショットです。
10月18日(土曜日)11時~16時 10月19日(日曜日)10時~15時 北山交流まつり
ぜひ見に来てください。お待ちしてます。
四ツ谷用水を歩く(大崎八幡宮から支倉堀まで)
9月25日(木曜日)9時30分~11時45分 企画員9人
 今回歩いた四ツ谷用水は、大崎八幡宮から支倉堀までと範囲を決め上流から下流へと辿りました。大崎八幡宮の太鼓橋から下を覗き、ここに水が流れていた様子を想像するところから講座が始まりました。用水跡をそのまま歩くことができないので、道路に出てはまた用水跡を歩くを繰り返し進みます。途中、伊達家祈願寺の龍寶寺に寄って山門、釈迦堂、不動堂、多宝塔、金堂と見学させていいただきました。
今回歩いた四ツ谷用水は、大崎八幡宮から支倉堀までと範囲を決め上流から下流へと辿りました。大崎八幡宮の太鼓橋から下を覗き、ここに水が流れていた様子を想像するところから講座が始まりました。用水跡をそのまま歩くことができないので、道路に出てはまた用水跡を歩くを繰り返し進みます。途中、伊達家祈願寺の龍寶寺に寄って山門、釈迦堂、不動堂、多宝塔、金堂と見学させていいただきました。
用水が北六番町に向かって斜めに流れ込むところや、支倉堀に流れを分 かつところにある分水井(ぶんすいせい)などただ歩いているだけでは見過ごしそうな小さな痕跡も逃さず見つけて四ツ谷用水のイメージを膨らませました。土橋通にあった御飼鳥屋敷(おかいどりやしき)跡は、用水の水を引き込んだ池があった場所で、現在は看護研修センターになっており、建物内に当時の井戸跡が残されていました。最後の支倉堀跡には当時の石垣を見ることができ、水量が多かったことがわかりました。今回は、草むらをかき分けたり、道とは言えないようなところを歩いたりと冒険心をくすぐるような内容で、企画員は「テレビの番組みたいだったね」と感想を言い合っていました。
かつところにある分水井(ぶんすいせい)などただ歩いているだけでは見過ごしそうな小さな痕跡も逃さず見つけて四ツ谷用水のイメージを膨らませました。土橋通にあった御飼鳥屋敷(おかいどりやしき)跡は、用水の水を引き込んだ池があった場所で、現在は看護研修センターになっており、建物内に当時の井戸跡が残されていました。最後の支倉堀跡には当時の石垣を見ることができ、水量が多かったことがわかりました。今回は、草むらをかき分けたり、道とは言えないようなところを歩いたりと冒険心をくすぐるような内容で、企画員は「テレビの番組みたいだったね」と感想を言い合っていました。
市民企画会議
7月17日(木曜日)10時00分~11時45分 企画員9人/8月28日(木曜日)10時00分~11時45分 企画員7人
へくり沢上流・下流と散策し、振り返りと今後のスケジュール確認を行いました。へくり沢を歩いた感動が大きくて、今後のことまで話し合う時間が取れず2回に渡っての会議になりました。
北山交流まつりに4月に散策した「新坂通探訪」を発表すること、それ以外の今後のスケジュールは下記のように決定しました。
・9月25日 四ツ谷用水散策(大崎八幡神社から支倉堀)
・10月30日 北山にあった「中の小川」(上流から尾根道、伊勢神明社と御嶽三吉神社)
・11月6日 北山にあった「中の小川」(下流、恩慶寺と千手観音協会)
・12月4日 北山にあった「北の小川」と「北山の流れ」(大法寺)
・3月12日 北山にあった「南の小川」(超光寺)
合間に企画会議も予定しています。どれもほとんどが暗渠になっているので、水の跡を探し歩く散策になりそうです。
へくり沢散歩道下流編
6月5日(木曜日)10時00分~12時00分 企画員10人
 前回解散場所の春日神社からへくり沢を歩きます。瀬田谷不動尊を見学していると、通りすがり(?)の男性が石切町の説明をしてくださいました。「石工七人衆」という初めて聞く言葉に後で詳しく調べてみようということになりました。小梨石材店さんの敷地内にへくり沢の流れがあるので、見学させていただきました。すると先程の男性が小梨さんとお話していて、また敷地内の説明もしていただけました。ありがとうございました。流路跡に沿って進み「姥ケ崎」と言われるかなり低くなっているところで休憩、写真は道路から覗き込むように撮ったものです。
前回解散場所の春日神社からへくり沢を歩きます。瀬田谷不動尊を見学していると、通りすがり(?)の男性が石切町の説明をしてくださいました。「石工七人衆」という初めて聞く言葉に後で詳しく調べてみようということになりました。小梨石材店さんの敷地内にへくり沢の流れがあるので、見学させていただきました。すると先程の男性が小梨さんとお話していて、また敷地内の説明もしていただけました。ありがとうございました。流路跡に沿って進み「姥ケ崎」と言われるかなり低くなっているところで休憩、写真は道路から覗き込むように撮ったものです。
 さらに進み、下見では危ないと判断してコースを変える予定だった階段が直されていたので「袖ケ崎」まで降りていくことになりました。20メートルの谷底を歩いて自然が作り出した地形や、そこに住めるようにした人間の知恵に感嘆し、周りを見上げながら進みました。弁慶岩といわれる岸壁を切って開いた「新坂」の辻標を見て、新坂通からここまで一本道だったことが解りました。最後に疲れた足を引きずって宮城県知事公館へ、ほっと一息ついて館内や庭園の見学をしました。
さらに進み、下見では危ないと判断してコースを変える予定だった階段が直されていたので「袖ケ崎」まで降りていくことになりました。20メートルの谷底を歩いて自然が作り出した地形や、そこに住めるようにした人間の知恵に感嘆し、周りを見上げながら進みました。弁慶岩といわれる岸壁を切って開いた「新坂」の辻標を見て、新坂通からここまで一本道だったことが解りました。最後に疲れた足を引きずって宮城県知事公館へ、ほっと一息ついて館内や庭園の見学をしました。
へくり沢散歩道上流編
5月15日(木曜日)10時00分から12時00分 企画員9人
 今回から企画員になった方々を交え、へくり沢を散策しました。最初は、旧「半子町」にある壽徳寺を見学しました。丸門寺と呼ばれる所以になった仙台市登録文化財の山門や、宮城県の古庭園「池泉回遊式庭園」などじっくりと見せていただきました。「こんな奥に庭園があるのは気付かなかった」「かなり古いお墓があって興味深い」などの感想が聞かれました。
今回から企画員になった方々を交え、へくり沢を散策しました。最初は、旧「半子町」にある壽徳寺を見学しました。丸門寺と呼ばれる所以になった仙台市登録文化財の山門や、宮城県の古庭園「池泉回遊式庭園」などじっくりと見せていただきました。「こんな奥に庭園があるのは気付かなかった」「かなり古いお墓があって興味深い」などの感想が聞かれました。

国見小学校脇から、本題のへくり沢を探索しました。通称「あか道」と呼ばれる舗装が赤い道を下流に向かって歩きました。水路を感じるくねくねした道が続きます。途中「たこ公園」で最近塗り直して鮮やかな赤のたこ遊具を確認して、最後の春日神社に着きました。四谷用水との立体交差が描いてある絵を見て、「こう流れてたんだね」「この絵がなかったら解らなかったね」と話し合い、次回の下流編を楽しみに解散しました。
新坂通り探訪坂と桜とお寺さん
4月10日(木曜日)10時00分から12時00分 企画員4人参加者9人

令和7年度、最初の活動は新しい仲間を増やすこと。
お花見に行く計画に、新規会員を募集することになりました。
新規の10人と一緒に、新坂通の謎を解きながら桜を鑑賞しました。
これは、歯学部沿いの桜並木です。
 新坂通は、広瀬町にある「新坂」に向かって延びる一本道です。
新坂通は、広瀬町にある「新坂」に向かって延びる一本道です。
大学病院が建設される以前は、輪王寺のある北山の通りから
まっすぐ繋がっていました。大学病院建設時に今までどおり通り抜
けをという請願に応え、現在も常時通り抜けできるようになってい
ます。これは、裏門近くにあるモンキーパズルの木です。

医学部の中庭には掬水の池があり、その周囲にはたくさんの桜が
咲いていました。昔、掬水の池は四谷用水から水を引いていたそ
うです。
これは、ひときわ大きな桜の木で、参加者から大きな歓声が聞か
れました。

「伊達家四代藩主綱村公(幼名亀千代)が榴ヶ岡公園に約100本の
枝垂れ桜を植樹した、その時の一株が成長し樹齢300有余年、今尚
生育健在旺盛」と2007年頃の立て札に書いてある「亀千代桜」
民家の庭にあるので、宮城第一高等学校側から見学させていただきま
した。
 今回の講座は新規参加者を迎えるために、企画員が事前に調べ説明も
今回の講座は新規参加者を迎えるために、企画員が事前に調べ説明も
することになりました。専門家ではない目線からの解説が「ちょうど
いいテンポと内容だった」とお褒めの言葉をいただきました。参加者
から企画員になる方もいて、今後の活動が賑やかになりそうです。
これは、中島丁公園の見事な桜。
講座情報
| 添付ファイル |
|---|
