ページID:5137
更新日:2025年3月25日

ここから本文です。
令和5年度「田子の魅力発信広報部」(複数年)

第9回定例会
2023年12月21日

第9回令和5年12月21日(木曜日)10時00分~11時30分 会場 第2会議室
テーマ「11月の企画講座の内容と自主研修」のふりかえり
外部講師を招き実施した企画講座と自主研修について振り返りました。まち歩きの企画から実施までを行っている団体である「奥州・仙台おもてなし集団伊達武将隊」の松尾芭蕉氏をお迎えした自主研修は、「プロの「受講生を楽しませる手法」や「まち歩き」の心得など大変参考になった。」、「他の講座でも、案内を依頼したい。」「一緒に行ったまち歩きは、受講生として話に引き込まれた。」などの感想がありました。自主研修をふまえ、次年度のまち歩きの時期や手法を考え次年度企画を計画したいと話し合いました。

第8回11月30日(木曜日)自主研修会
「地域の魅力をいかに伝えるか」自然・文化・歴史 地域案内人の心得
講師:奥州・仙台おもてなし集団伊達武将隊 松尾芭蕉氏
広報部の研修として11月16日のまち歩きに引き続き松尾芭蕉さんに講師をお願いし、仙台を中心とした観光案内や様々な広報活動を担うプロとして、参加してくださった方々にいかに楽しんでいただくための伝え方や注意点、企画の仕方などを教えていただきました。「地域の魅力を掘り起こし、磨き、知らせて誇りある地域を目指そう。」と地域案内人の意義について触れられ、「田子の魅力発信広報部」の部員は、あらためて地域活動の意欲が高まっていた様でした。



第7回 11月16日(木曜日) 冬のまち歩き(参考テキスト①田子今昔物語1 企画運営
講師:伊達武将隊 松尾芭蕉氏(専用テキストあり) 田子の魅力発信広報部
1 オリエンテーション ①体調の確認 ②コースの説明 ③質疑応答 ④準備運動
2(出発)田子市民センター⇒田子西地区⇒田子大橋⇒Q七北田川サイクリングロード⇒帰館
企画講座に参加していただいた方は田子以外(区外、市外、県外)の方が多く、講座の広報の仕方、タイトル、外部講師の選定等広報としては、SNSの効果が大きく、参加者中にはインスタグラムに写真を投稿されている方もいらして、投稿の際は#(ハッシュタグ)仙台田子を付けて頂ければとお願いしました。翌日には、何人の方が仙台市田子として、田子で見られた野鳥の姿を投稿されていました。
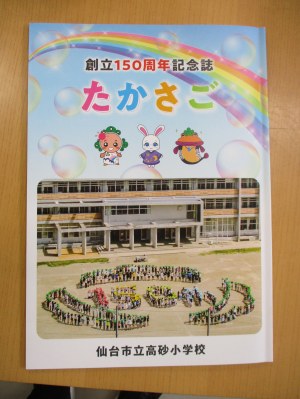
第6回 10月19日(木曜日)テーマ「11月実施の企画講座 当日の役割分担と行程確認」他
11月に企画講座・自主研修について内容の確認とそれぞれの日程について確認し、まち歩きの役割分担を決めました。併せて、当日の講師「冠川地元学の会」と一緒に小学校のまち探検に行くボランティアもお願いすることが出来ました。また、今年高砂小学校が創立150周年を迎え発行された記念誌の内容を踏まえ、田子地域に活かせる資料作りの検討を行いました。

トピック 10月5日(木曜日) 宮城県順絶滅危惧種ミズアオイの種を採取に行きました。
11月の企画講座の下見の際、講師の奥州・仙台 おもてなし集団 伊達武将隊(外部サイトへリンク) 松尾芭蕉氏が田子地域内で発見した「ミズアオイ」の種を採取に行ってきました。順絶滅危惧種という貴重な植物は、次年度の地域の小学校での環境学習に役立つ物であるため、関係各所に許可を取り、芭蕉さんと共に採取してきました。
第5回 9月21日(木曜日)テーマ「11月の企画講座の内容と自主研修」について
11月16日(木曜日)企画講座 伊達武将隊 松尾芭蕉さんとあるく
「野鳥観察と撮影テクニック」講座
11月30日(木曜日)七北田川の自然を知ろう~と自主研修「まち歩きでの魅力的な話し方、伝え方」の進捗状況についてセンターからの報告を受け,講座を通して、自分たちが何を学べるかを検討しました。また、「地域の魅力を外部の視点で掘り下げ、まち歩きの案内のスキルアップを図りたいとの意見がありました。
第6回 10月19日(木曜日)テーマ「11月実施の企画講座 当日の役割分担と行程確認」他
11月に企画講座・自主研修について内容の確認とそれぞれの日程について確認し、まち歩きの役割分担を決めました。併せて、当日の講師「冠川地元学の会」と一緒に小学校のまち探検に行くボランティアもお願いすることが出来ました。また、今年高砂小学校が創立150周年を迎え発行された記念誌の内容を踏まえ、田子地域に活かせる資料作りの検討を行いました。

第4回 7月20日(木曜日)定例会(6月のまち歩きの反省と次回まち歩きの企画会)
6月のまち歩きを実施して
「御船曳堀・お蔵前など痕跡がないところでお話をする難しさがある、旧字名を記した地図などを資料として利用しても良いのでは。」とのご意見がありました。福田町は、江戸時代から続く古い町なので時代ごとに案内するテーマがあり、時代ごとのテーマを決め案内していこうということになりました。
次回のまち歩きの企画では、七北田低地の渡り鳥や野鳥の写真を含めた景観を残そう。と企画を進めています。また、田子村の旧字名の由来など、聞き取りが出来る範囲で調査をしていく予定です。

広報部企画「田子まちあるき『福田町をあるく』」行ってきました。
第3回6月15日(木曜日)10時00分~12時00分(企画講座 田子まちあるき「福田町をあるく」
①四野山観音堂→⓶観音堂西橋→③扇町6丁目公園(お船曳堀跡)→④福田自転車橋(お蔵前)→帰路
①四野山観音堂では、雲洞院のご住職小松啓祐氏より観音堂や、雲洞院の歴史についてお伺いすることができました。大正時代に奉納された柳の観音様の絵馬や観音様が出てきたとされる柳の木の洞の一部を拝見させていただきました。その柳の木は、劣化を防ぐため薬剤の処理を施されたそうです。その後,仙台市の史跡になっている石碑も解説していただきました。


⓶観音堂西橋→③扇町6丁目公園(お船曳堀について)
観音堂から梅田川に向かい、観音堂西橋を渡って扇町6丁目公園に向かいました。広報部員から、当時の御船曳堀りの形状や有り様などを説明し、参加者から梅田川の水の活用などの質問を受けていました。一艘の平田船に80俵のお米を積んで運んでいた話もすることが出来ました。


④福田自転車橋(鶴巻御蔵)と仙台藩の物流について
扇町6丁目公園から土手沿いに梅田川沿いに歩き、七北田川との合流点付近まで歩きました。蒲生の御船入堀から鶴巻まで運び、鶴巻にあった御蔵に荷を一旦上げてから、城下までの水路で運ぶ拠点となった場所です。この付近は、昔の字名に当時をしのばせる名前がついています。広報部員からの解説で当時に思いをはせることができたでしょうか。川の合流点から海に向かって川幅が一段と広がっていきます。オオヨシキリやカワウ等野鳥も見られ、自然豊かな場所です。曇り空でしたが、川風が心地よい一日でした。
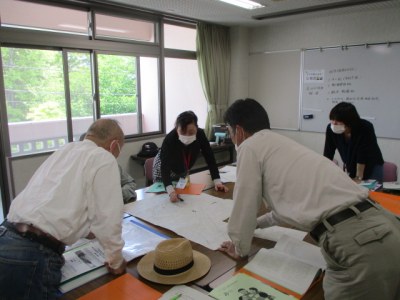
第2回 5月18日(木曜日)テーマ「6月の田子まち歩き」のコースと内容について
4月に企画した内容をもとに話し合い、コースと休憩やトイレやコンビニエンスストアーの場所を確認し、題材毎に、説明する担当者を決めていきまた。
観音堂から出発し、観音堂西橋(御船曳堀跡)から梅田川の土手沿いを歩き、かつてのお舟入堀の御蔵付近から七北田川との合流地点、参道を通って観音堂へ戻ってくるコースで、ウォーキングも楽しめる講座になりそうです。

第1回 4月20日(木曜日)テーマ「令和5年度の活動予定と企画会」
昨年度の受講生を中心に、企画検討会を行いました。企画員の方から、「令和3年度に歩けなかった鶴巻地区を紹介したい。」とのご意見が上がり、前回とは視点を変えたまち歩きのコースを考えました。また、2回目は「田子の自然を知るためには、冬鳥を中心にした七北田川沿岸の自然観察会が良いのでは。」との案が上がり、白鳥や雁が身近に見られる地域環境を案内する冬のコースの計画を検討していきます。
お問い合わせ
田子市民センターまで
