ページID:5174
更新日:2025年3月26日

ここから本文です。
令和6年度 福室老壮大学

令和6年度 福室老壮大学 講座レポート
2025年3月27日
9.閉講式・記念コンサート『サックスとピアノのコンサート』

 2月28日(金曜日)
2月28日(金曜日)
閉講式に先立ち、記念コンサートとして、Music LIfeの大道美由貴氏と千葉千寿子氏をお招きし、「サックスとピアノのコンサート」を開催しました。
コンサートでは、「青葉城恋歌」や「川の流れのように」、「津軽海峡冬景色」などの有名な楽曲を演奏していただきました。どの曲もサックスとピアノが織りなす美しい音色が、ホールに響いていました。また、途中にイントロクイズもあり、とても楽しいひと時を過ごすことができました。
後半で閉講式を挙行しました。令和6年度は、継続受講の20年表彰3名、15年表彰2名、10年表彰3名に表彰状と記念写真が贈呈されました。また、皆勤賞の26名には記念の花鉢が贈られました。
令和6年度の福室老壮大学はこれで終了ですが、来年度も5月から様々な講座を予定しています。これからも老壮大学で共に学びましょう!
8.講話『江戸時代の福室村と田子村の七北田川鮭留紛争』

 1月29日(水曜日)
1月29日(水曜日)
講師として、仙台市歴史民俗資料館の畑井洋樹氏をお招きし、「江戸時代の福室村と田子村の七北田川鮭留紛争」と題して、お話しを伺いました。
江戸時代、鮭は仙台藩から幕府への献上品になる程魅力的な産物でした。
七北田川上流の田子村では鮭をとる権利が藩から認められていましたが、下流の福室村がその利権を犯し、鮭を取ってしまった事件がありました。
その背景には、七北田川の流路変更や、初代藩主伊達政宗から二代忠宗への代替わりがあり、その期に乗じて、利権を得ようと画策した人々がいたという説明がありました。
受講生からは「歴史につながる土地に、住んでいること身近に感じます。」「福室地区に40年以上住んでいるが地元の歴史については、何も知識がなかったので、今回は興味深い話を聞けて大変参考になりました。とてもロマンを感じました。」という感想をいただきました。
7.講話『笑いの万能薬 シルバー川柳』

 12月18日(水曜日)
12月18日(水曜日)
講師として、みやぎシルバーネット編集長の千葉雅俊氏をお招きし、「笑いの万能薬 シルバー川柳」と題して、お話を伺いました。
初めに、シルバー川柳傑作選や、末期がんと闘いながら川柳を投稿した方のお話などをご紹介いただいた後、作句のコツを教えていただきました。
作句の際には、読む人を笑わせる、共感させることを第一に目指すこと。ほかにも、他人と異なる着眼点を持つことや、時間をおいて推敲を行うことが大切とのお話がありました。
その後、実際に受講生も作句に挑戦しました。短い時間でしたが、いくつもの良作が生まれたようでした。
受講生からは「川柳で楽しい日々を過ごしたいです。」「川柳は難しいけど楽しいです。作者の方に脱帽です。」「作句のセンスはないものの、ほかの方の作品を知りとても楽しい時間になりました。」という感想が寄せられました。
6.講話『オーラルフレイル予防(高齢者の口の健康)』


11月27日(水曜日)
講師として、歯科医師で日本笑い学会東北支部長のスマイリーチバ氏をお招きし、「オーラルフレイル予防(高齢者の口の健康)」と題して、お話を伺いました。
フレイルとは健康な状態と要介護状態の中間の段階を指します。そのフレイル状態に至る前段階として、口から食べ物をこぼす、ものがうまく呑み込めない、滑舌が悪くなるといった口に関する兆候が見られ、それらをオーラルフレイル(プレフレイル)と呼びます。
オーラルフレイル予防に「笑い」はとても有効で、口の周りの筋肉を鍛えるほかにも、脳の動きを活性化したり、自立神経を整えてくれたり、血行を促進したり・・・。「笑い」は様々な面で身体にプラス効果が期待できると教えていただきました。
先生のユーモアたっぷりの健康講座で、会場は「笑い」にあふれていました。
受講生からは「笑うことの大切さを知りました。」「笑う門には福来る~。人生には笑いが必要ですね。」「巧みな話術での講話、引き込まれて拝聴しました。」という感想が寄せられました。
5.講話『家の片づけ・終活の極意』

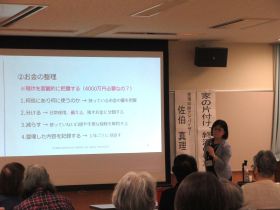
10月23日(水曜日)
講師として、整理収納アドバイザーの佐伯真理氏をお招きし、「家の片づけ・終活の極意」と題して、終活についてお話を伺いました。
ものを整理しようと考えると、「捨てる」ことを考えますが、終活として整理する場合は大切なものを「選ぶ」ことが大切。医療や介護の情報整理や名義変更、各種サービスの解約手続き、相続準備の必要性も教えていただきました。
人生の整理とは大切にしてきた物や事などの「残したいもの」を後世に伝えること。これからの人生、「やりたいこと」と「やりたくないこと」を選んで、自分らしい人生を送ることが大切と教えていただきました。
受講生からは「早目の準備、心掛けの大切さを改めて覚悟しなければと存じます。」「終活を始めて久しいですが、今回の講座はこれから自分が整理しなければならないことがよくわかり、これからも続けていきたいと思います。」「先生ご自身の経験をまじえてのお話、大変参考になりました。」という感想が寄せられました。
4.鑑賞・実技『美しい日本の童謡・唱歌』


9月25日(水曜日)
講師として、声楽家の星久美子先生をお招きし、「美しい日本の童謡・唱歌」と題して、馴染み深い楽曲を先生のピアノ演奏に合わせて歌いました。
今回は9月の講座ということで、『赤とんぼ』や『十五夜お月さん』など、秋の歌を中心に選曲していただきました。
歌の合間に、その曲が作られた時代背景や、歌詞に込められた作者の想いなどを、ユーモアを交えながら詳しく教えていただきました。
受講生たちは、歌を口ずさんだ子どものころを思い出しているようでした。
受講生からは「久しぶりに大きく口を開き声を出しました。また、先生のお話でたくさん知識が増えました。」「先生のご指導で楽しく歌うことができました。日本語の美しさを再確認できました。」
「久しぶりの唱歌はたいへん懐かしく、何十年ぶりで歌うことができました。」「故郷で小学生時代、母が唄っていたのを思い出しました。」という感想が寄せられました。
3.講話『特殊詐欺の最新情報について』


7月31日(水曜日)
講師として、仙台東警察署 生活安全課 生活安全係の三石様・松崎様をお招きし、「特殊詐欺の最新情報について」と題して最近の手口や対策方法について学びました。
宮城県だけでも、特殊詐欺被害は去年一年間で約350件発生し、約9億7400万円の被害が発生している状況です。
最近はパソコンの修理費用やウェブサイトの未納料金などの名目で電子マネーなどをだましとる「架空請求詐欺」が多く発生。架空請求への支払い方法として、コンビニ収納代行サービスを悪用し、コンビニで支払うように指示されるケースもあるそうです。
ほかにも「オレオレ詐欺」など、さまざまな特殊詐欺がありますが、それらへの一般的な対策として
- 電話に特殊詐欺電話撃退装置を取り付ける(常に留守番電話設定でも効果あり)
- プラス(+)で始まる電話番号(国際電話)はとらない
- 電話でお金・キャッシュカードの話がでたら一旦電話を切る
- 普段から家族とコミュニケーションをとり、何かあったらすぐに相談する
などが有効であると教えていただきました。
受講生からは「最新の詐欺の手口について詳しく話され、たいへん参考になりました。」「不審に思ったら家族に確認することが大切だと思った。」という感想が寄せられました。
2.実技『家でもできる簡単な筋トレ・ストレッチ』


6月26日(水曜日)
講師として、仙台市健康増進センター 運動指導員の今野志子氏をお招きし、「家でもできる簡単な筋トレ・ストレッチ」を学びました。
なぜ普段の生活に運動が必要なのでしょうか。それは、運動することで、転倒予防、認知機能活性化、生活習慣病予防、心肺機能向上、ストレス解消、うつ病の予防等、さまざまなメリットがあるからです。先生から運動の大切さを伺った後、1時間ほど実際に身体を動かしました。
今回の講座では、通常のストレッチだけではなく、両手を別々に動かしたり、声を出しながら身体を動かすことで、認知症予防に特に効果がある運動も行いました。梅雨で湿度の高い日でしたが、受講生たちは気持ちよく身体を動かしていました。
受講生からは「家でも毎日できるようにがんばりたいと思います。」「体が軽くなりリラックスできました。」という感想が寄せられました。
1.開講式・記念コンサート『二胡の調べ』


5月29日(水曜日)
いよいよ5月から老壮大学が開講します。今年は66名の皆さんと一緒に学びます。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、今回は開講式に続いて、記念コンサート「二胡の調べ」を開催しました。
日本二胡学院有志の皆さんに出演していただき、『埴生の宿』や『荒城の月』『見上げてごらん夜の星を』など、受講生になじみ深い曲を演奏していただきました。また、演奏に加えて二胡の歴史や楽器自体の成り立ちを伺うことで、二胡への理解を深めるよい機会となりました。
受講生からは「2本の弦だけで豊かな音色が響き、楽しいひと時を過ごすことができました。」「二胡の演奏で、すばらしい一年のスタートになりました。」という感想が寄せられました。
