ページID:4714
更新日:2025年3月25日

ここから本文です。
令和5年度 落合栗生実年学級
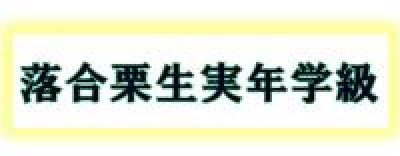
令和5年度落合栗生実年学級 講座レポート
2024年1月23日
第1回 開講式・「楽しく健活セミナー チョコレートの世界へようこそ」


5月18日木曜日、真夏のような日差しが降り注ぐ中、「落合栗生実年学級」が開講しました。今年度は昨年度より少し多い、50名の方にご参加いただきました。
第一部では、開講式を行いました。厳かな雰囲気の中で行われた開講式に、受講生は少し緊張しつつも、その表情からはこれから訪れる新たな学びへの期待が見られました。
第二部では、株式会社明治 食育担当の百足奈々氏より、「チョコレートの世界へようこそ」という題目でご講話をいただきました。カカオの5000年の歴史や、カカオが原産国から日本に来るまでの過程のお話を聞き、普段食べているチョコレートがとても貴重なものであることを学びました。
原産地の違いによる味の違いも体験した受講生は、チョコレートの奥深さを感じたようでした。
第2回 公開講座「初夏の風かおるコンサート」

 6月15日、第2回 公開講座「初夏の風かおるコンサート」を行いました。今回は落合栗生地区社会福祉協議会と共催としました。さらに地域の方々にもご参加いただき、総勢約90名となりました。
6月15日、第2回 公開講座「初夏の風かおるコンサート」を行いました。今回は落合栗生地区社会福祉協議会と共催としました。さらに地域の方々にもご参加いただき、総勢約90名となりました。
奏者は仙台フィルハーモニー管弦楽団で活躍中の長谷川 康 氏(バイオリン)、木立 至 氏(オーボエ)と、東 歩美 氏(ピアノ)です。「乾杯の歌」から華やかに始まり、素晴らしい演奏を聴かせてくださいました。
また、オーボエの音が鳴る仕組みについてのお話や、バイオリンの聴き比べなど楽しいコーナーもあり、楽器の豆知識についても聞くことができました。
中にはアンコール曲を聴いて思い出がよみがえり、涙を流す受講生の姿も。プロ奏者による生の音色と懐かしい曲に包まれ、感動の時間となりました。
第3回 防災出前講座「特殊詐欺の手口について」&茶話会


7月20日に第3回講座「防犯出前講座 特殊詐欺の手口について」を実施しました。講師は仙台市防犯協会の本田 勉 氏です。
講師の方から県内の特殊詐欺の状況や、防犯の意識を日頃から養っていくことの大切さについてお話を聞きました。
1時間の講話終了後、希望者で茶話会を行い、グループごとに情報交換の時間を持ちました。
「家ではこんな詐欺対策をしているよ!」「こんな怪しいメールが届いたの!」など話題は尽きませんでした。
茶話会の後には「普段の講座で他の受講生と話す機会があまりないので楽しかった」という感想が聞かれました。
第4回「五郎八姫が愛した里・栗生」


久しぶりの雨とともに秋の気配も感じる9月21日(木曜日)、第4回講座「五郎八姫が愛した里・栗生」が開催されました。
講師は落合栗生歴史愛好会の会長で、落合栗生地区連合町内会の会長でもある庄子 隆 氏と、事務局長で栗生3丁目町内会長でもある鈴木 憲一 氏です。
講師のお二人は、伊達政宗公と愛姫の娘である五郎八姫が、現在の栗生である西館にかつて住んでいたこと、その際栗生の人々と素敵な交流があったということを、スライドを用いて分かりやすく話されていました。
また、五郎八姫の居住地近くにある史跡には、キリスト教との関連があることにも触れていただきました。
自分が長らく住んでいるこの地域にこんな歴史があったのかと、受講生は驚きを隠せない様子。
久しぶりに涼しさを感じるこの日、地元の歴史とその史跡にスポットを当てた講座は、受講生一人ひとりの知的好奇心を大いに充足させる時間となりました。
第5回 「ブックトークで知る本のよさ」


金木犀の香りに包まれた爽やかな秋晴れの10月19日(木曜日)、仙台市図書館ブックトークボランティア「ランプ」のお二方を講師にお招きし、第5回「ブックトークで知る本のよさ」を開催しました。
はじめに現代書「ことばのかたち」などを取り上げたブックトークを聞き、言葉の大切さについて考えました。
続いて古典の名作「枕草子」や「源氏物語」、「今昔物語」を取り上げたブックトークを披露。
受講生は古典の世界と現代がつながっていることに驚きつつ、ふふっと笑みをこぼしていました。
ブックトークを通じて、様々な角度から本のよさについて考えることができました。
受講生からは「普段触れることのできない世界に触れることができるので本が大好きです」「紹介してもらった古典のマンガを読んでみようと思います」といった感想が聞かれました。
第6回「ニュースポーツに挑戦!」


晴れ渡った秋の11月16日(木曜日)、第6回「ニュースポーツに挑戦!」を行いました。第2回に続いて落合栗生地区社会福祉協議会と合同で行い、40名以上の方が参加しました。
講師は青葉区中央市民センターから社会教育主事の三浦 健輔氏、市川 仁氏のお二人です。
準備運動の後、説明を聞いてさっそく競技に挑戦しました。
最初は個人でターゲット、わなげ、バッゴー、ターゲットリングをそれぞれ体験しました。
はじめてのニュースポーツに戸惑う人もいましたが、コツを掴んでくると、互いに教え合う様子が見られました。
休憩の後、今度はボッチャに挑戦です。今回は特別ルールとして3人1組のチームで対戦しました。
接戦になると、あちらこちらから大きな拍手と歓声が上がります。
最後にはお互いのプレーを讃え合い、大盛況のうちに講座は終了。
社会福祉協議会の方々ともニュースポーツを通して楽しく交流ができ、笑顔あふれる時間となりました。
第7回「森のクリスマスリースを作りましょう」


クリスマスが間近に迫る12月21日、第7回「森のクリスマスリースを作りましょう」を開催しました。今回教えてくださるのはM no niwaの横山美由紀氏です。講師から今回使う草花について説明を聞き、リースの材料を広げると、森の香りが部屋いっぱいに広がりました。
まずは葉類をまとめ、小さなブーケを作ります。この段階から既に各自の色が出てきます。次に、作ったブーケをリース台にくくり付けていきます。受講生は「難しい」と言いつつも、納得いくまでじっくりと取り組んでいました。最後にユーカリの葉や赤い芙蓉の実などを好きなところに付けて、リースは完成です。それぞれの個性が表現された、素敵なリースが出来上がりました。
最後に完成したリースのアピールポイントを発表すると、称賛の声と拍手が飛び交いました。今回のリース作りを通じて、柔らかい雰囲気の中受講生同士が心を通わすことができました。
第8回「モンゴルの代表的楽器・馬頭琴演奏とあっぺとっぺの助の新春初笑い」

 1月18日(木曜日)、第8回実年学級を開催しました。落合栗生地区社会福祉協議会のサロン参加者と地域の方々にもご参加いただき、総勢約100名の方と一緒に楽しみました。
1月18日(木曜日)、第8回実年学級を開催しました。落合栗生地区社会福祉協議会のサロン参加者と地域の方々にもご参加いただき、総勢約100名の方と一緒に楽しみました。
今回は馬頭琴奏者の渡辺圭一氏と素人演芸ひとり座「あっぺとっぺの助」の山崎孜氏にお越しいただきました。
第一部は馬頭琴の鑑賞です。モンゴルの伝統曲や日本の曲が披露されました。また、モンゴルと日本の友好のために活動されている山崎氏より馬頭琴やモンゴルの風景についてのお話も聞くことができました。
第二部は「あっぺとっぺの助」の新春初笑いです。方言を用いたトークが披露されると、会場は大爆笑に包まれました。
講座後に実施したアンケートからは、「馬頭琴の音色はパワフルな中にも哀愁があり、心にしみるものがありました」「新年早々悲しい災害が起き、笑えていなかったのですが、今日は思いっきり笑えました」という感想が聞かれました。
この1年もこの日のように感動と笑いに溢れる年になることを願っています。
第9回「東北に演芸の花を咲かせる」


2月15日(木曜日)、第9回実年学級を開催しました。今年度最後の講座となる今回は、魅知国花座 席亭 白津 守康氏をお迎えし、お話ししていただきました。落語の歴史や裏話、なぞかけなどバラエティに富んだお話しに、興味深く楽しく聞き入っていました。浪曲の際には「日本一!」「待ってました!」「たっぷり!」と掛け声もかかり、大いに盛り上がりました。受講生からは「笑って元気になりました」などの声も聞かれました。
講座終了後、閉講式を行いました。今年度全9回の講座を写真などで振り返り、懐かしさもこみ上げてきます。支倉運営委員長のあいさつの後、最後にお世話になった運営委員の方々へのに拍手が送られ、今年度の全講座が終了となりました。受講生から「どの回も工夫されていて良かった」「馬頭琴やバイオリンなどの生演奏が素晴らしかった。参加して良かった」など感想をいただきました。一年間ありがとうございました。
