ページID:5283
更新日:2025年3月19日

ここから本文です。
令和6年度 七郷老壮大学
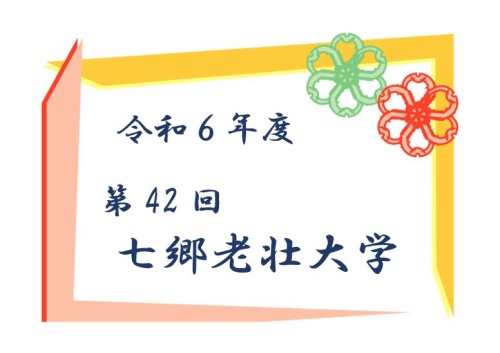
講座レポート
2025年3月16日

第10回「消費者被害の対処法および未然防止策について」



3月12日(水曜日)、第42回 七郷老壮大学 閉講式・修了式を行いました。令和6年度の修了生は73名、うち2月までの皆勤賞は32名でした。各地区代表者への修了証授与の後、七郷老壮大学運営委員会副委員長の鈴木勇二さんが受講生を代表して謝辞を述べました。その後、「消費者被害の対処法および未然防止策について」と題し、宮城県消費生活センターの藤本英夫氏に記念の講話をいただきました。
講話では、具体的な例として映像を交えながら、特殊詐欺、点検商法、通信販売等様々な消費者被害の事例について教えていただきました。「自分は大丈夫!」と過信せず、少しでも変だと思った時にはすぐに相談する重要さについて、改めて知ることができました。
受講生からは、「カタログでの買い物の返品ができず、捨てたことがあります。クーリングオフの話はもっと早く知りたかったです。」「最近は高齢者をだます手口が多く、家族には注意を受けていても、日中一人で家にいることが多いので不安があります。自分には関係ないと思っていたので、気を付けなければと思いました。」などの感想が寄せられました。
閉講式終了後は、運営委員会自主企画の懇親会が開催され、受講生による様々な演芸披露が行われました。
令和6年度も全10回の講座を開催することができました。講師の皆様、受講生ならびに運営委員の皆様、1年間ありがとうございました。
第9回「天気の一般的な知識について」


2月5日(水曜日)、第9回「天気の一般的な知識について」と題し、仙台管区気象台 予報課 予報官の熊谷浩也氏に講話をいただきました。
70名の出席者は普段テレビで目にする天気予報について、今まで知らなかった用語や地域・時間の細分、どのように気象観測を行っているのか等について学びました。『時々』と『一時』の違いや、『昼過ぎ』や『明け方』は何時から何時までを示すのか等、時折会場からは「なるほど」「そうだったのか」という声も挙がり、目から鱗が落ちるような知識を得られたようでした。
受講生からは、「『所により』の『所』とはどこを示すのかや降水確率の時間の細分についてなど、今後天気予報を見るときの参考になりました。」「今まで気象観測所に行ったことがないので色々な機材についての予備知識がなく、初めて聞かせていただいたことで、最近の天気予報の仕組みが分かったような気がしました。」などの感想が寄せられました。
第8回「伊達政宗公の夢と支倉常長の足跡」


1月8日(水曜日)、第8回「伊達政宗公の夢と支倉常長の足跡」と題し、奥州・仙台おもてなし集団 伊達武将隊の支倉常長氏に講話をいただきました。
当日は69名が出席し、伊達家・伊達政宗公についてや支倉常長の生涯、常長の海外との関わりについてお話しいただきました。(もしかすると、あの時はこうだったのかもしれない…)という回想や、再現をはさみながらのお話は会場を沸かせ、和やかな雰囲気の中で学ぶことができました。
受講生からは、「政宗公と支倉常長の関係、常長の人間性について、真面目で素晴らしい方で政宗公の信頼も大きかったということが印象に残りました。」「支倉常長像が世界に7体あり、海外で高く評価されていたということを知りました。何百年も前に船で大変な思いをしながら、メキシコ・スペイン・イタリアまで行ったことに驚きです。」などの感想が寄せられました。
第7回「よ~っこらSHOW(笑)タイム ~音楽で楽しく認知症予防~」


12月11日(水曜日)、第7回「よ~っこらSHOW(笑)タイム ~音楽で楽しく認知症予防~」と題し、音楽療法士の山下圭氏に、音楽に合わせて認知症予防のためのトレーニングを行っていただきました。
最初は静かに話を聞いていた69名の出席者も、山下氏の軽快なトークにつられて、次第に笑顔があふれていきました。最初に手を動かす脳トレをした後、歌を歌いながら手足を動かすトレーニングをしました。思うように手足を左右違う動きにできなかったり、歌につられてしまったりと苦戦しながらも、会場は終始笑いが絶えず、楽しくトレーニングができました。
受講生からは、「初めての体験でした。笑いながらの認知症音楽療法、最高でした。2つのことを同時にすることがなかなか難しく、認知機能低下に注意しようと思いました。」「音楽を通し、楽しく認知症療法ができるということを初めて知ることができました。音楽療法の良さを実感でき楽しかったです。」などの感想が寄せられました。
第6回「チョコレートの世界へようこそ!」


11月13日(水曜日)、第6回「チョコレートの世界へようこそ!」と題し、株式会社 明治の中屋沙希子さんに講話をいただきました。
大好きなチョコレートの話が聞けるためか、72名の出席者の多くは講座が始まる前から気分が高揚している様子でした。まず、カカオ豆からチョコレートができるまでの写真や映像を見ながら学んだ後、カカオやチョコレートの歴史について教えていただきました。その後、2種類のチョコレートをゆっくりと食べ比べることでそれぞれの味の違いを感じながら、日本におけるチョコレートの文化を学びました。
受講生からは、「意外と知らなかったチョコレートの奥が深い話にびっくりです。カカオが神々の食べ物であるとは知りませんでした。」「カカオが枝ではなく、幹に直接花や実がなることにびっくりです。木が三階くらいの高さまで伸びるのもびっくりでした。映像やお話から、地球温暖化によるカカオ農家さんの苦労が感じられました。」などの感想が寄せられました。
第5回「リフレッシュ健康体操」


10月9日(水曜日)、運営委員会自主企画として第5回「リフレッシュ健康体操」と題し、健康運動指導士の佐々木郁子先生に、椅子に座ったまま行えるストレッチ等の軽体操を教えていただきました。
毎年恒例となった佐々木先生の講座を楽しみにしていた受講者も多く、当日は78名が出席しました。最初に口や足などのストレッチをして体をほぐした後、簡単な脳トレを行いました。数字を数えながら手を動かすという単純な脳トレですが、二つのことを同時に行わなければならず、想像よりも難しいとの声もありました。その後は、音楽に合わせて歌いながらテンポよく体を動かしたりと、皆さん楽しそうに運動されていました。
受講生からは、「リラックスして楽しくできました。音に合わせて身体を動かすのは楽しいです。身体を意識して使う心がけが大事だと思いました。」「背中が丸いのでストレッチがとても参考になりました。手足の指が少し不自由なので、毎日時間をみて動かすよう努力します。」などの感想が寄せられました。
第4回「健康づくりに役立つ 薬の話」


共催:公益財団法人 仙台市健康福祉事業団
9月11日(水曜日)、第4回「健康づくりに役立つ 薬の話」と題し、公益社団法人 仙台市薬剤師会 会長の北村哲治氏に講話をいただきました。
74名の出席者の中には、普段から薬を服用している方も多く、薬の正しい飲み方を再確認する良い機会となりました。また、薬以外にもタバコや認知症、コロナウイルスを含む感染症の対策等、身近な話題についても詳しく知ることができました。
受講生からは、「なにげなく飲んでいたクスリに“リスク”があることも知り、きちんと薬を飲むことを自覚しました。」「塗り薬の塗り方、外側から内側に塗ったほうが良いと初めて知りました。ジェネリック医薬品を常用してきましたが、次回から薬局の方に相談をしてみます。」などの感想が寄せられました。
第3回「衰えは声から現れる 発声トレーニングで誤嚥予防」


7月10日(水曜日)、第3回「衰えは声から現れる 発声トレーニングで誤嚥予防」と題し、ボイストレーナーであるTAKAHASHI VOICE PRODUCTION 代表の高橋寿和先生に、ボイストレーニング法を指導していただきました。
当日は75名が出席し、呼吸法の違い・声帯の動き・なぜ嚥下障害が起こるのか等を学んだ後、実際に声を出していくつかのトレーニングを行いました。はっきりとした大きな声を出すためには、口の周りの筋肉だけではなく全身の力を使わなければならず、想像以上に疲れてしまったという方も多く見られました。
受講生からは、「ボイストレーニングは歌だけだと思っていたのでとてもためになり、家でもしてみようと思います。舌筋を鍛えるということを続けようと思います。」「誤嚥の話は聞いたことがありますが、こんなに奥深いとは知りませんでした。声帯・声門閉鎖筋をいかに鍛えるかを知ることができました。大変勉強になりました。」などの感想が寄せられました。
第2回「七郷を学ぶ(第8回)」


6月12日(水曜日)、運営委員会自主企画として第2回「七郷を学ぶ(第8回)」と題し、老壮大学運営委員会の運営委員長でもある、郷土史研究会の松木達雄さんに講話をいただきました。
毎年恒例となった歴史講話も今年で8回目を迎え、73名の出席者とともに、七郷地域の歴史について学びを深めました。
その中でも、5000年前の第1浜堤から2000年前の第2浜堤にかけての地域を中心に、四ツ谷、笹新田、藤田、深沼等について学び、受講生の皆さんは昔の七郷地域に思いをはせていました。
受講生からは、「深沼に住んで50年になりますが、知らないことがたくさんありました。特に屋号を覚えるのが大変でした。神明社、八大龍王碑、湊神社の通称を資料で知ることができて良かったです。“お法印さん”と呼ばれていたのですね。」「とても興味深いお話ありがとうございました。七郷の出身ではないので、これからも地域について勉強させていただきたいと思います。」などの感想が寄せられました。
第1回「お札の話(偽造防止技術)」



5月8日(水曜日)、第42回 七郷老壮大学が開講し、94名の方が入学しました。開講式には85名の受講者が出席し、第1回「お札の話(偽造防止技術)」と題し、日本銀行 仙台支店の郡司暢久さんと西大立目知穂さんに講話をいただきました。
講話の途中、実際にお札を手に取って光にすかしたり手で触って感触を確かめたりと、偽造防止技術にはどんなものがあるのかを確認しました。また、レプリカの一億円を持ち上げて重さがどれくらいあるのかを体験する光景も見られました。
受講生からは、「偽造されないようにお札に多数のしかけがあるのにびっくりです。1万円札が1g、1円玉と同じ重さ等教えていただき、新しいお札にも興味がわきました。」「お札の話、特に新札の話におどろきでした。日本銀行に行くことがないので、お話に心打たれ、お札を大切に扱いたいと思いました。」などの感想が寄せられました。
その後は運営委員会総会が開催され、令和5年度の会計報告や令和6年度の運営委員役員等が承認されて閉会となりました。
