ページID:8601
更新日:2025年3月25日

ここから本文です。
令和6年度 城前大学
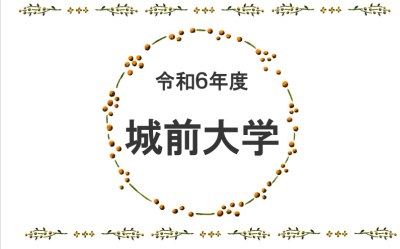
令和6年度 城前大学を開講しました。
2024年5月16日


5月16日 第1回 開講記念講演 懐かし仙台 昔を語る会「8ミリ映像で脳を元気に」
令和6年度城前大学が開講となりました。本年度は62名の受講生にご応募いただき初回を迎えることができました。
NPO法人20世紀アーカイブ仙台 理事長の坂本英紀氏をお迎えしました第1回講演は、昔懐かしの道具を実際に拝見し、また懐かしの風景を映像で振り返る昭和の時代にタイムスリップしたかのような内容でした。昔を思い出すことは脳の活性化につながるということですが、講座後には、「子どものころに戻ったようにほっこりしました」「昭和の時代をとても懐かしく当時を思い出しながら、昭和は本当に良い時代だったなあと痛感しました」「コロナがあり休学していましたがまた来れるようになりうれしく思っております。懐かしい映像をみながら、歌もあり来て良かったと思っております」といった感想をいただきました。


6月20日 第2回 講話『しっかり食べて、元気に百歳まで歩こう!』 講師に仙台オープン病院院長 土屋 誉 氏をお招きしました。百歳まで元気に過ごすためには、歩くこと、口腔ケア、握力がとても重要だそうです。また、不足しがちな亜鉛についても詳しく教えていただきました。亜鉛が不足すると口内炎や脱毛、傷が治りにくい、風邪をひきやすいといったさまざまな症状が現れてしまうそうです。受講生はメモをとりながら熱心に耳を傾けていました。講座後には「楽しく教えていただきとても有意義な時間でした」「食べて、筋肉をつけ、身体活動、健康で長生き100歳まで」「先生のお話を大事にして生活すると百歳まで歩けそうです」「とても勉強になりました。先生の他の講座も聞いてみたいです」といった感想をいただきました。


7月18日 第3回 講話『紅麹問題から考える~薬と健康食品の飲み合わせについて~』 講師にエムツー調剤薬局 薬局事業部マネージャー 菅野 隆文 氏をお招きしました。現在もまだ調査中の紅麹サプリによる健康被害の問題を例に、薬と健康食品の飲み合わせについて詳しく解説いただきました。安全に健康食品を服用するために、お薬を飲んでいる方は医師への確認、飲み合わせに関しては薬剤師への相談をしてくださいということです。受講生はうなずきながら再確認されていたり、先生の一語一語に聞き入っている様子でした。講座後には「飲み合わせの注意点が分かった」「薬をとりすぎると中毒になる」「今まで薬に関して関心が薄かったが、今日のお話しによって関心が高まりました」といった感想をいただきました。


9月19日 第4回 民話と唱歌「ふるさと」を手話で 講師に民話語り部 穀田 千賀子 氏をお招きしました。今回は穀田先生の創作民話「とげぬき地蔵」を穀田先生の故郷気仙沼の方言で語っていただきました。なかなか聞いた事のない方言もありましたが、先生の語り方、表情としぐさで話の流れは感じることができました。唱歌「ふるさと」は手話をしながらの歌唱でしたが、この手話をしながらというのが右脳と左脳を同時に動かすということで脳トレになるのだそうです。歌いながらの手話はなかなか難しいものでしたが、受講生のみなさん一生懸命取り組まれていました。「あっという間だった」「わからない部分もありましたが最後は涙がでました」「民話に感動し、手話は楽しかった」「もう一度受講したい」といった感想をいただきました。


11月21日 第5回 軽体操『フレイル予防運動』 講師にいずみの杜診療所 理学療法士 望月 昴 氏をお招きしました。座ってでもできる軽体操は簡単ではあるけれども、肩甲骨や筋肉を意識するとじんわり汗ばむような運動でした。急に寒くなってきた時期ではありましたが、体がぽかぽかしてきて、途中で上着を脱ぐ受講生もおり、厳しい寒さへと向かうこの季節にはぴったりの運動でした。運動には脳トレも交えていただき、講座終了後には「脳トレが難しかったが楽しかった」「間違えたけど楽しかった」といった感想をいただきました。また、「みんなで体を動かすことが楽しくて良かった」「家でもできる運動なので続けていきたい」「毎日取り入れたいと思います」といった感想もいただきました。講話に関しては「バランスの良い食事、運動、口内を清潔に、を頑張っていきたいです」といった声も聞かれました。

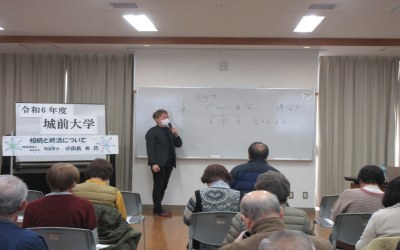
12月19日 第6回 講話『相続と終活について』講師に一般社団法人 あすとわ 小田島 央 氏をお招きしました。大変難しい内容ではありましたが、「家族でお話をしたり何かを始めてみたりするきっかけになればと思っています」という先生のお言葉通り、先生の元へ依頼のあった実例なども交え、大変わかりやすくお話いただきました。相続や終活については知識が必要になりますが、まずは何から始めたらいいのか、どんなことが必要になるのかなどの基本となるところを教えていただきましたので、受講生からも「できることから実行していきたい」といった感想を多くいただきました。他にも「家族で色々と話し合いの必要性を強く感じました」「問題を先送りしないことの大事さを改めて考えさせられました」「今まで考えたこともなかったことを教えていただきました」「色々と考えさせされました。他人ごとではないなぁと思いました」といった感想をいただきました。
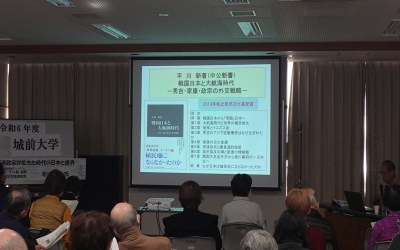

1月16日 第7回 講話『伊達政宗の生きた時代の世界と日本』 講師に宮城県慶長使節船ミュージアム サン・ファン館館長 東北大学名誉教授 平川 新 氏をお招きしました。先生からは「世界史と日本史を連動させてみるとおもしろい」といったお話がありましたが、受講生からも「世界からみた日本。違う角度からの講義、大変大きな学びでした」といった感想をいただきました。他にも「歴史に興味がわいてきました」「歴史が苦手な者ですが、とても楽しく勉強させていただきました」「とても興味深く拝聴しました。歴史好きですが点でつながっている部分が線になり、さらに興味を持って歴史に向き合うことができます。充実した時間でした」といった感想をいただき、歴史への関心の高さが伺えました。また、センターへのご意見としては「なかなかお会いできない平川先生を呼んでいただいてありがとうございました」「もっと知りたい、第二弾期待します」といった声をいただきました。



2月20日(木曜日) 第8回 閉講記念公演 『尺八コンサート』尺八奏者 大友 憧山 氏をお招きいたしました。従来の尺八のイメージとは大きく異なる、J-POPやジャズ、アニメソングなどを演奏いただきました。公演中には手拍子をしながらリズムをとる方や、目を閉じてじっくり聴き入る方など、思い思いが新たな尺八の世界に浸る時間となりました。尺八は長さが一尺八寸だから尺八という、といった名前の由来など、尺八についての知識も深めることができました。アンケートでは「音の世界に包み込まれ、夢の時間があっという間にすぎ、楽しい時間をありがとうございました」「はじめて尺八の曲を聴きました。さまざまなジャンルの曲を聴くことが出来、尺八のイメージが変わりました。尺八のお話も聞けて良かったです」「感激して涙がでました。はじめてでした」「尺八ってなんて素敵な音なんでしょう。高音の幅の広さ、低音の音の深み、もう一度お聴きしたいものです」といった感想が寄せられました。講座後の受講生とのお話のなかでも「尺八のイメージが変わった」「感動した」「ぜひまた聴かせていただきたい」といった声が多く聞かれました。
